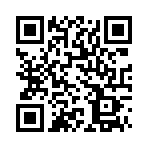2014年08月02日
第 23 回母乳育児シンポジウム「母乳育児の輪を広げよう」
あっという間に8月ですね~!
うみ・つきスタッフはほぼ全員集合(子どもの熱で一人お休み;;)して、
新スタッフのあこさんの歓迎&オーストラリア研修に行くtakakoさんの壮行会を兼ねて、
移転オープンした直江助産院にて
今年のいいお産の日や情報誌ぷかぷかについてのミーティングをしました~♪

持ち寄りディナーで美味しい時間♪
今日から熊本で母乳育児シンポジウムが始まります。
うみ・つきも熊本県助産師会会長の坂梨先生にお誘いいただき、パネル展示させていただきます。
とっても濃密な内容で、読んでるだけでも勉強になるなあと坂梨先生にご承諾いただき、お知らせ転送します。
詳しくは、
http://www.bonyu.or.jp/index.asp
<世界母乳週間 世界母乳の日>
2014 年 8 月 2 日(土)3 日(日)
第 23 回母乳育児シンポジウム「母乳育児の輪を広げよう」
主催:一般社団法人日本母乳の会
後援:ユニセフ 厚生労働省 日本産科婦人科学会 日本小児科学会 日本小児科医会 日本周産期・新生児医学会日本助産師会 日本看護協会 熊本県産婦人科医会、熊本県母性衛星学会、熊本小児科学会、熊本県小児科医会 熊本県看護協会 熊本県助産師会 熊本県 熊本市
8月2日 土
総合司会:蔵本 昭孝(産・熊本市民病院) 石笠 奈美(助・国立病院機構嬉野医療センタ—)
9:00 〜 9:30 挨拶開会挨拶: 近藤 裕一 第 23 回母乳育児シンポジウム 実行委員長 熊本市民病院 挨 拶: 山内 芳忠 日本母乳の会 代表理事 メッセージ:厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課(予定)
9:30 〜 11:00一般演題(1) ワークショップ (一般演題応募から)第 22 回第 23 回ワークショップ優秀演題 「妊娠中の乳房ケアを考える」「赤ちゃんの泣きを考える」
11:00 〜 11:302014 年「赤ちゃんにやさしい病院」認定証授与式挨拶・認定証授与:平林 国彦(ユニセフ東京事務所 所長)
11:30 〜 12:00 特別講演「赤ちゃんにやさしい病院推進運動と子どもの健康」講師:平林 国彦(ユニセフ東京事務所 所長) 司会:山内 芳忠(小・吉備国際看護大学)
<12:00〜13:00 昼食・休憩>
13:00 〜 13:30報 告(1):妊娠中の乳頭ケアの実際・母親の実態調査(BFH 施設の調査から) 妊娠中の乳頭ケアは日本の母乳育児支援として行われてきましたが、近年、欧米文化の影響で、不必要という意見も 出されています。BFH 施設のアンケート調査から妊娠中の乳頭ケアの実態について、報告します講師:山縣 威日 (産・サンクリニック/日本母乳の会学術委員会)
13:30〜 15:45 シンポジウムI 「変化する社会と母乳育児支援」急激な社会の変化が生みだした人間関係の希薄さは、子育ての場にも影響を及ぼしています。母乳育児支援には産 科医療の現場だけではなく、幅広い支援が必要です。様々面から考えていきます司会:吉永 宗義(小/日本赤十字九州国際看護大学/宗像市) 薬袋 由美(助・山梨県立中央病院/甲府市)
1)基調提言日本のお産が戦後どう変容してきたか、助産・産褥・新生児の保健指導、今一番足りない親子関係の支援。助産師 の必要性・重要性、そして周産期医療に関わる人へ、支援のあり方を伝えたい久保 紀夫(産・国立病院機構九州医療センター/福岡市)
2)社会的に困難な状況におかれた母子への支援様々な問題を抱えている目の前の母親に、今できることは何なのか。中絶や乳児院へ児を預けるなど子どもの存在を忘れたいと言う方も多い。地域で「命の授業」を行っているので、伝えたい太田 純代(助・福岡赤十字病院/福岡市)
3)母乳育児を通して、母親として育つために—支援に何が必要か愛されたという実感を持つことができない女性が出産し、母親になれないことが多い。母親になって行く過程を 支援する大変さ、そして母親への一歩を踏みだすための支援とは、を考えていきます熊谷 孝子(栄・くまがい産婦人科/大分)
4)母乳育児を地域・社会に広げるために—BFH認定病院の影響退院後、母親が自信を持って母乳育児を続けるために、地域での広がりをどうするか。BFH の活動と地域の母乳の 広がりについて、また、十三市民病院の取り組みを伝えます
<15:45〜16:00 休憩>
16:00〜16:45 市民公開講座 教育講演「スマホ時代の母乳育児」ここ数年のスマートホンの普及は社会に急激に大きな変化をもたらしています。若い母親達がスマートホンで育児を していることを医療関係者はどの程度知っているでしょうか。医療者はその実態を知り、どうすべきか提言します講師:佐藤 和夫(小・国立病院機構九州医療センター/福岡市) 司会:近藤 裕一(小・熊本市民病院/熊本市)
16:45 〜 17:45
17:45 〜 18:00
18:30 〜 20:30
ポスター前発表 一般演題応募演題からポスタ—前で質疑応答 日本母乳の会会員報告会懇親会 ホテル日航熊本
8月3日 日
平林 円(小・大阪市立十三市民病院/大阪市)総合司会:森下 哲哉(産) 森下産婦人科医院(福岡市)木庭 礼子(保) 熊本市役所 子ども支援課 (熊本市)
8:45 〜 9:45 一般演題(2)
9:45〜 11:45 シンポジウムII 「母乳育児支援:取り組みのベーシック」妊娠した母親の 95%以上が母乳育児を望んでいるのに、1 カ月健診では平均 50%。99%の母親が病院・診療所で 出産する現在、産後入院中に、それぞれの職種ができること、困難な事を話しあいます司会:沼田 修 (小・長岡赤十字病院/長岡市) 桑原 美保(助・熊本市民病院/熊本市)
1)なぜ、産科医が母乳育児支援をするのか—産科診療所の産科医から- 世代間伝承の途絶のために日本の文化から一度消え去った母乳育児を復活することが、日本の社会の諸問題の大 きな原因である少子化に対する最も効率の良い対策です。その実現の中心は産科医であり、その役割を考えます柚原 健男(産・ゆのはら産婦人科医院/熊本市)
2)0.1.2 日目の母子ケアのポイント—産科診療所の助産師から出産後、母乳が出始めるまでの 3 日間、頻回授乳を含めて、母親をどのように支えていくか考えたい原田 美由紀(助・産科婦人科久米クリニック/いちき串木野市)
3)補足検討チームを作って— 病院小児科医から母乳不足に対して自信を持って対応するために院内デ―タを基に検証して、を考えていきます佐藤 広樹(小・組合立諏訪中央病院/茅野市)
4)病院内に母乳育児を定着させるために—病院産婦人科医から多数のスタッフ、移動の多い病院にて、母乳育児支援の考えを浸透させていった経過と苦労したことをお話ししま す房 正規 (産/加古川西市民病院・加古川市)
5)小児科医、多職種との連携—病院助産師から母親を支えるためには多職種での支援が必要です。新しい取り組みを始める時の経験等をお話しします
11:45 〜 12:10報 告(2) こども未来財団委託研究報告「産後2週間健診への提言」
<12:10〜13:10 昼食・休憩>
13:10 〜 13:40山本 優子(助/仙台市立病院・仙台市)講師:西巻 滋 (小/横浜市立大学附属病院・横浜市)報 告(3)「震災を忘れない:福島のお母さんはかなりポジテイブ!」3.11 の東日本大震災後、まだ多くの方々が避難生活を余儀なくされています。原子力発電所の事故による災害に会 った福島県での母乳育児支援の現状をお話しします講師:氏家 二郎(小・国立病院機構福島病院/須賀川市) 教育セミナー実践編 「母乳育児支援の問題を考えよう」
13:40 〜 15:30母乳育児支援で、ぶつかる問題を皆さんで考えましょう。QA 方式で、気軽に知識と実践を司会:久野 正 (小・聖マリア病院/久留米市)
1)「母親の母乳分泌と赤ちゃんの生理を科学する」講師:杉本 充弘(産・日本赤十字社医療センター/東京)
2)「母乳育児支援で悩む低血糖の問題について」
3)何でも質問してみよう
15:30 〜 15:40閉会挨拶:久保 紀夫 第 23 回母乳育児シンポジウム副実行委員長 挨 拶:田中 滋己 第 24 回母乳育児シンポジウム実行委員長挨拶講師:畑崎 喜芳(小・富山県立中央病院/富山市)
うみ・つきスタッフはほぼ全員集合(子どもの熱で一人お休み;;)して、
新スタッフのあこさんの歓迎&オーストラリア研修に行くtakakoさんの壮行会を兼ねて、
移転オープンした直江助産院にて
今年のいいお産の日や情報誌ぷかぷかについてのミーティングをしました~♪

持ち寄りディナーで美味しい時間♪
今日から熊本で母乳育児シンポジウムが始まります。
うみ・つきも熊本県助産師会会長の坂梨先生にお誘いいただき、パネル展示させていただきます。
とっても濃密な内容で、読んでるだけでも勉強になるなあと坂梨先生にご承諾いただき、お知らせ転送します。
詳しくは、
http://www.bonyu.or.jp/index.asp
<世界母乳週間 世界母乳の日>
2014 年 8 月 2 日(土)3 日(日)
第 23 回母乳育児シンポジウム「母乳育児の輪を広げよう」
主催:一般社団法人日本母乳の会
後援:ユニセフ 厚生労働省 日本産科婦人科学会 日本小児科学会 日本小児科医会 日本周産期・新生児医学会日本助産師会 日本看護協会 熊本県産婦人科医会、熊本県母性衛星学会、熊本小児科学会、熊本県小児科医会 熊本県看護協会 熊本県助産師会 熊本県 熊本市
8月2日 土
総合司会:蔵本 昭孝(産・熊本市民病院) 石笠 奈美(助・国立病院機構嬉野医療センタ—)
9:00 〜 9:30 挨拶開会挨拶: 近藤 裕一 第 23 回母乳育児シンポジウム 実行委員長 熊本市民病院 挨 拶: 山内 芳忠 日本母乳の会 代表理事 メッセージ:厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課(予定)
9:30 〜 11:00一般演題(1) ワークショップ (一般演題応募から)第 22 回第 23 回ワークショップ優秀演題 「妊娠中の乳房ケアを考える」「赤ちゃんの泣きを考える」
11:00 〜 11:302014 年「赤ちゃんにやさしい病院」認定証授与式挨拶・認定証授与:平林 国彦(ユニセフ東京事務所 所長)
11:30 〜 12:00 特別講演「赤ちゃんにやさしい病院推進運動と子どもの健康」講師:平林 国彦(ユニセフ東京事務所 所長) 司会:山内 芳忠(小・吉備国際看護大学)
<12:00〜13:00 昼食・休憩>
13:00 〜 13:30報 告(1):妊娠中の乳頭ケアの実際・母親の実態調査(BFH 施設の調査から) 妊娠中の乳頭ケアは日本の母乳育児支援として行われてきましたが、近年、欧米文化の影響で、不必要という意見も 出されています。BFH 施設のアンケート調査から妊娠中の乳頭ケアの実態について、報告します講師:山縣 威日 (産・サンクリニック/日本母乳の会学術委員会)
13:30〜 15:45 シンポジウムI 「変化する社会と母乳育児支援」急激な社会の変化が生みだした人間関係の希薄さは、子育ての場にも影響を及ぼしています。母乳育児支援には産 科医療の現場だけではなく、幅広い支援が必要です。様々面から考えていきます司会:吉永 宗義(小/日本赤十字九州国際看護大学/宗像市) 薬袋 由美(助・山梨県立中央病院/甲府市)
1)基調提言日本のお産が戦後どう変容してきたか、助産・産褥・新生児の保健指導、今一番足りない親子関係の支援。助産師 の必要性・重要性、そして周産期医療に関わる人へ、支援のあり方を伝えたい久保 紀夫(産・国立病院機構九州医療センター/福岡市)
2)社会的に困難な状況におかれた母子への支援様々な問題を抱えている目の前の母親に、今できることは何なのか。中絶や乳児院へ児を預けるなど子どもの存在を忘れたいと言う方も多い。地域で「命の授業」を行っているので、伝えたい太田 純代(助・福岡赤十字病院/福岡市)
3)母乳育児を通して、母親として育つために—支援に何が必要か愛されたという実感を持つことができない女性が出産し、母親になれないことが多い。母親になって行く過程を 支援する大変さ、そして母親への一歩を踏みだすための支援とは、を考えていきます熊谷 孝子(栄・くまがい産婦人科/大分)
4)母乳育児を地域・社会に広げるために—BFH認定病院の影響退院後、母親が自信を持って母乳育児を続けるために、地域での広がりをどうするか。BFH の活動と地域の母乳の 広がりについて、また、十三市民病院の取り組みを伝えます
<15:45〜16:00 休憩>
16:00〜16:45 市民公開講座 教育講演「スマホ時代の母乳育児」ここ数年のスマートホンの普及は社会に急激に大きな変化をもたらしています。若い母親達がスマートホンで育児を していることを医療関係者はどの程度知っているでしょうか。医療者はその実態を知り、どうすべきか提言します講師:佐藤 和夫(小・国立病院機構九州医療センター/福岡市) 司会:近藤 裕一(小・熊本市民病院/熊本市)
16:45 〜 17:45
17:45 〜 18:00
18:30 〜 20:30
ポスター前発表 一般演題応募演題からポスタ—前で質疑応答 日本母乳の会会員報告会懇親会 ホテル日航熊本
8月3日 日
平林 円(小・大阪市立十三市民病院/大阪市)総合司会:森下 哲哉(産) 森下産婦人科医院(福岡市)木庭 礼子(保) 熊本市役所 子ども支援課 (熊本市)
8:45 〜 9:45 一般演題(2)
9:45〜 11:45 シンポジウムII 「母乳育児支援:取り組みのベーシック」妊娠した母親の 95%以上が母乳育児を望んでいるのに、1 カ月健診では平均 50%。99%の母親が病院・診療所で 出産する現在、産後入院中に、それぞれの職種ができること、困難な事を話しあいます司会:沼田 修 (小・長岡赤十字病院/長岡市) 桑原 美保(助・熊本市民病院/熊本市)
1)なぜ、産科医が母乳育児支援をするのか—産科診療所の産科医から- 世代間伝承の途絶のために日本の文化から一度消え去った母乳育児を復活することが、日本の社会の諸問題の大 きな原因である少子化に対する最も効率の良い対策です。その実現の中心は産科医であり、その役割を考えます柚原 健男(産・ゆのはら産婦人科医院/熊本市)
2)0.1.2 日目の母子ケアのポイント—産科診療所の助産師から出産後、母乳が出始めるまでの 3 日間、頻回授乳を含めて、母親をどのように支えていくか考えたい原田 美由紀(助・産科婦人科久米クリニック/いちき串木野市)
3)補足検討チームを作って— 病院小児科医から母乳不足に対して自信を持って対応するために院内デ―タを基に検証して、を考えていきます佐藤 広樹(小・組合立諏訪中央病院/茅野市)
4)病院内に母乳育児を定着させるために—病院産婦人科医から多数のスタッフ、移動の多い病院にて、母乳育児支援の考えを浸透させていった経過と苦労したことをお話ししま す房 正規 (産/加古川西市民病院・加古川市)
5)小児科医、多職種との連携—病院助産師から母親を支えるためには多職種での支援が必要です。新しい取り組みを始める時の経験等をお話しします
11:45 〜 12:10報 告(2) こども未来財団委託研究報告「産後2週間健診への提言」
<12:10〜13:10 昼食・休憩>
13:10 〜 13:40山本 優子(助/仙台市立病院・仙台市)講師:西巻 滋 (小/横浜市立大学附属病院・横浜市)報 告(3)「震災を忘れない:福島のお母さんはかなりポジテイブ!」3.11 の東日本大震災後、まだ多くの方々が避難生活を余儀なくされています。原子力発電所の事故による災害に会 った福島県での母乳育児支援の現状をお話しします講師:氏家 二郎(小・国立病院機構福島病院/須賀川市) 教育セミナー実践編 「母乳育児支援の問題を考えよう」
13:40 〜 15:30母乳育児支援で、ぶつかる問題を皆さんで考えましょう。QA 方式で、気軽に知識と実践を司会:久野 正 (小・聖マリア病院/久留米市)
1)「母親の母乳分泌と赤ちゃんの生理を科学する」講師:杉本 充弘(産・日本赤十字社医療センター/東京)
2)「母乳育児支援で悩む低血糖の問題について」
3)何でも質問してみよう
15:30 〜 15:40閉会挨拶:久保 紀夫 第 23 回母乳育児シンポジウム副実行委員長 挨 拶:田中 滋己 第 24 回母乳育児シンポジウム実行委員長挨拶講師:畑崎 喜芳(小・富山県立中央病院/富山市)
『和の国 発酵アカデミー』修了生による発酵講座のシェアランチ会
免疫学講座(免疫力を高める生活について) 〜人間のもつ内面の力に向き合う〜
赤ちゃんのやわらか抱き方講座のお知らせ
癒しの雑草の森で、お泊り可能なヨガイベント♪
夏といえば!ナースアウト♪
夏のコンサートのお知らせ♪
免疫学講座(免疫力を高める生活について) 〜人間のもつ内面の力に向き合う〜
赤ちゃんのやわらか抱き方講座のお知らせ
癒しの雑草の森で、お泊り可能なヨガイベント♪
夏といえば!ナースアウト♪
夏のコンサートのお知らせ♪